【ゆっくり解説 】聖徳太子一族の滅亡理由!!!
HTML-код
- Опубликовано: 5 фев 2025
- 「やばい古代史」では、古代史に焦点を当てて歴史を紐解いていく番組です。
我々はどこから来たのか。その鍵を古代史から読み解きます。
※この動画は、過去に起こった出来事をわかりやすく伝えることを目的としています。視聴者に衝撃を与えるような目的はございせん。
※動画内に、死を連想させるような言葉を出てきますが、関係者を冒涜したり行動を助長するような意図は一切ございません。
※動画内の素材は全て引用であり、著作権や肖像権を侵害する目的は一切ございません。
著作権などに関するお問い合わせはこちらのアドレスまでお願い致します。
yabaikodaishi@gmail.com


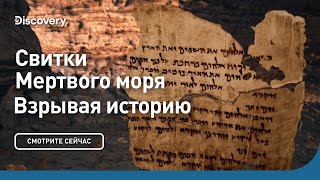

![I.N "HALLUCINATION" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/n5B5q1Hwt_U/mqdefault.jpg)




聖徳太子と蘇我馬子が編纂した「天皇記」と「国記」が中大兄皇子(天智天皇)に破棄され消失したのが残念
出雲神社の箱なんかに残ってないかなあ😢
あるとこでは山城はうぬぼれが強く人望がなかったからと聞いたな。
蘇我氏はあくまで実行犯だからね。
会ったことあるけど、態度悪かったよ
蘇我氏は皇族ですよ。だって古事記より古い天寿国繍帳には稲目の娘堅塩媛がおおきさきとされている。大后は皇族しかなれなかったから、堅塩媛の父親稲目は皇族となる。
ペディによると「天寿国繍帳」は以下が全文だね
辛巳の年(推古天皇29年・西暦621年)12月21日、聖徳太子の母・穴穂部間人皇女(間人皇后)が亡くなり、翌年2月22日には太子自身も亡くなってしまった。これを悲しみ嘆いた太子の妃・橘大郎女は、推古天皇(祖母にあたる)にこう申し上げた。「太子と母の穴穂部間人皇后とは、申し合わせたかのように相次いで逝ってしまった。太子は『世の中は空しい仮のもので、仏法のみが真実である』と仰せになった。太子は天寿国に往生したのだが、その国の様子は目に見えない。せめて、図像によって太子の往生の様子を見たい」と。これを聞いた推古天皇はもっともなことと感じ、采女らに命じて繡帷二帳を作らせた。画者(図柄を描いた者)は東漢末賢(やまとのあやのまけん)、高麗加西溢(こまのかせい)、漢奴加己利(あやのぬかこり)であり、令者(制作を指揮した者)は椋部秦久麻(くらべのはだのくま)である。
(飯田瑞穂による復元『原文』からの読み下し大意)
@@MedakaNoBooこれ全文じゃないよ。銘文には最初の部分に欽明天皇や稲目の系譜が書かれているのだが、銘文の現代語訳はこの系譜抜きのものが紹介されることがおおい。名伊奈米系譜部分には
巷奇大臣名は伊奈米足尼の女、名は吉多し比弥乃弥己等為大后と為す。
とまあ欽明が稲目の娘堅塩媛を皇后にしたと書いてあって稲目が皇族なのを暗示しているんだが、みんな妙なことに無視するんだ。??
冒頭部分のことかな?
斯帰斯麻 宮治天下 天皇名阿 米久爾意
斯波留支 比里爾波 乃弥己等 娶巷奇大
臣名伊奈 米足尼女 名吉多斯 比弥乃弥
己等為大 后生名多 至波奈等 已比乃弥
己等妹名 等已弥
欽明帝(※1)などは大臣の娘ら(※2)を、奇しくも巷(ちまた:庶民)より娶りて大后とし、姓(かばね)を『橘』などとした(**1, **2)
欽明帝の時代には臣下の娘を大后とした前例がある、って意味だね
だとすると、ウソは困るよ
姓(かばね)を持つのは臣下の証(あかし)であり皇族ではない、とても基礎的な誤解だよね
【脚注】
※1:「斯帰斯麻宮(しきしまのみや『師木島の大宮』)」に坐(おわし)まして天の下を治めし天皇、名を「阿米久爾意斯波留支比里爾波乃弥己(あめくにおしはるきひろにわのひこ『天国押波流岐広庭命』)」
※2:大臣の名より「伊奈 米足尼女(いなめのたらしびめ)」という、名は「吉多斯 比弥乃弥己(きたしひめのみこ『岐多斯比売(堅塩媛)』)」たちである
【補足】
**1:太后の生名(姓)は「多至波奈(たちばな『橘』」と、続き……
**2:彼女の「已比乃弥(おとひめ)」から自分たちの娘にも「比賣(ひめ)」と名づけるようになった、例えば……と続く
ちなみに、わたしは聖徳太子が摂政というのは誤りで、実質のところ蘇我馬子が大王だったと思っている、大王とは天皇だったのかがちょっと難しいところだけどね、だというに都合の悪い資料があるなあって感じかな